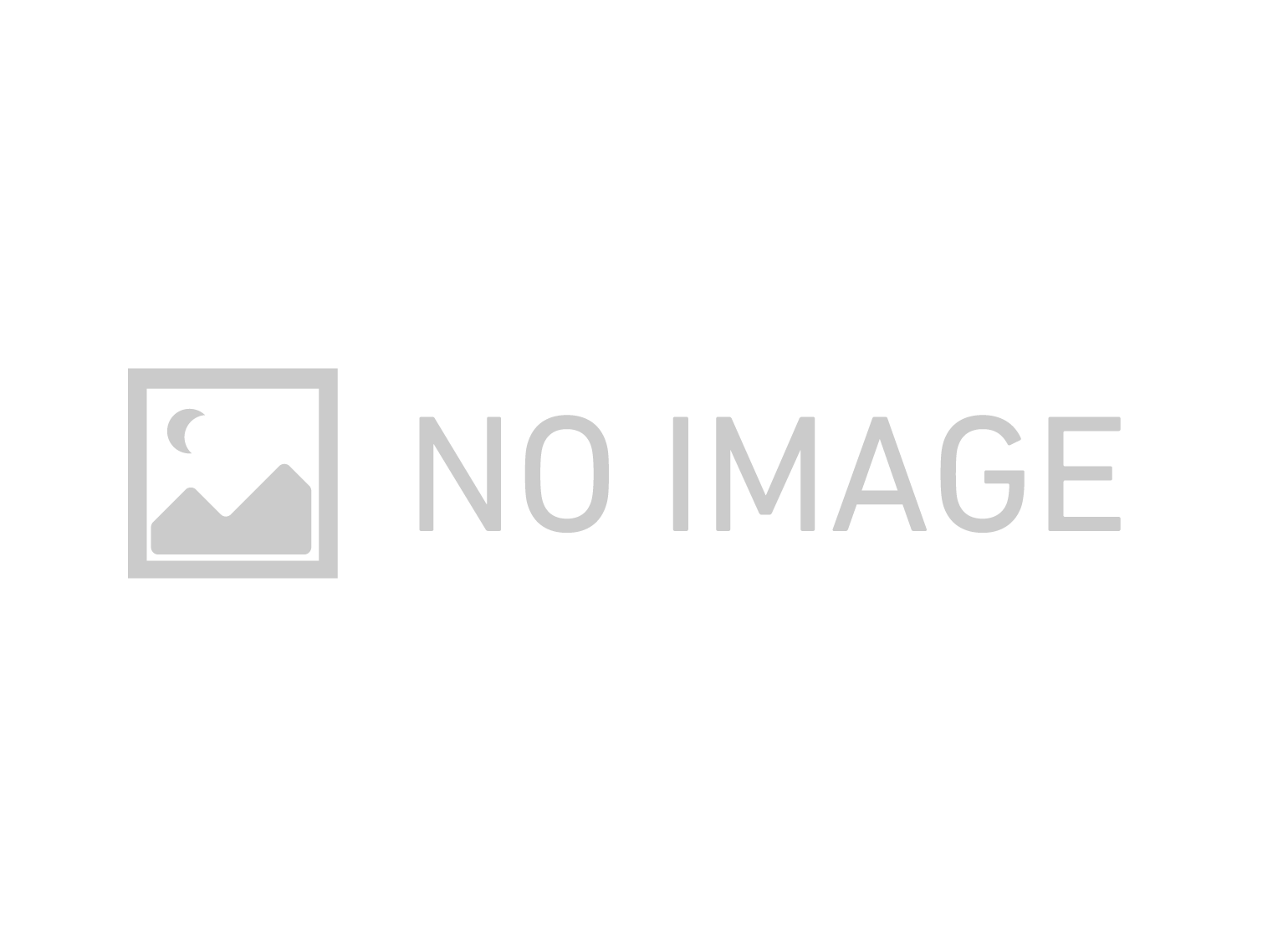日本で初めて世界遺産に登録された場所、それは姫路城(白鷺城)です。
兵庫県姫路市にある「姫路城」は、1993(平成5)年、奈良の法隆寺などと合わせて世界文化遺産に登録されました。2023年12月には世界遺産登録30周年を迎えます。日本に残る城跡の中でももっとも大規模で、白い姿が美しい姫路城。木造建築の最高傑作とも称されており、場内の多くの建築物が国宝に指定されています。2015年には約6年間に及ぶ保存修理工事を終え、いっそう美しく蘇りました。
この記事では、姫路城の見どころや歴史、姫路城にまつわる伝説についてご紹介していきます。
TOP画像: shiii/PIXTA
世界遺産・国宝、姫路城の特徴は?-「連立式天守」と白い城壁
特徴① 四つの天守-大天守と三つの小天守

姫路城の連立天守
姫路城の特徴といえばやはり天守。「連立式天守」と呼ばれていますが、どういうことかというと、四つの天守が四角形を描くように連なって建っているということです。
四つのうち大きい天守がひとつだけあり、「大天守」呼ばれています。四角の東南側にあたる隅に建っています。
ほかの三つの天守は「小天守(こてんしゅ)」と呼ばれており、それぞれ「西小天守」「乾(いぬい)小天守」「東小天守」と呼ばれています。大天守、三つの小天守はいずれも国宝です。
大天守は見かけが5重なので5階建てに見えますが、実際は地下1階、地上6階の7階建て。高さは約31.5m。実は江戸時代から残る12の天守の中でもっとも高いのが姫路城なのです。ちなみに、二番目に高いのは長野県にある松本城で、約25mです。
特徴② 真っ白な城壁-火災防止のための漆喰塗りに

近くで見ても真っ白(写真:PIXSTAR/PIXTA)
姫路城はその真っ白な美しい見た目から「白鷺城(ひめじじょう/はくろじょう)」とも呼ばれますが、真っ白に塗られているのには理由があります。ひとつは城主の権力を示すため。もうひとつは、火を防ぐためでした。
姫路城が築城された頃は火縄銃が普及していましたが、敵に火縄銃で攻められても延焼しないようにと漆喰が塗られました。姫路城の白い塗装は「白漆喰総塗籠め造り(しろしっくいそうぬりごめづくり)」と呼ばれています。
姫路城は姫山という山の上に立っているので、市内の様々な場所から目に入り、存在感の強さを感じさせます。真っ白な外観と連なる天守。美しさも防御力も兼ね備えた姫路城は国宝・世界遺産にふさわしい貫禄があります。
見どころ① 大天守の地下から五階までを貫く2本の柱

階段の横にある東大柱(写真:tanemu385/PIXTA)
姫路城の大天守は構造上、横揺れに弱いのですが、そこを補うために地下1階から5階までを大きな2本の柱が貫いています。東大柱の1階〜5階部分は築城当時のままで残っています。
見どころ② 敵の攻撃を退ける仕掛けいろいろ
姫路城には敵から攻められたときのための防御の仕掛けがいろいろとあります。
■「狭間」
櫓や土塀などには攻撃用の小さな穴が開けられていて、これを「狭間」と呼びます。姫路城には円形や三角形など、6種類の狭間があります。縦長の長方形のものが矢を放つためで、他の形のものは鉄砲を撃つための狭間です。
■迷路のような城内道
枝分かれする道や、人ひとりがやっと通れるような門(「るの門」)などがあり、敵の侵入を阻みます。
■「扇の勾配」
姫路城は天守にもいろいろな仕掛けがあります。石垣は上にいくほど急勾配になっており、開いた扇の曲線に似ているので「扇の勾配」と呼ばれています。登るのは容易ではありません。
■「石落とし」
そして石垣の上には「石落とし」と呼ばれる仕掛けも。狭間の一種で、鉄砲を撃つなどの攻撃をして下に迫る敵を退けました。
城内も、階段が迷路のように配置されていたり、階段を閉じる蓋や、攻撃のための隠れ部屋などが設けられています。

長方形、三角形など、さまざまな形の「狭間」(写真:m.Taira/PIXTA)

画面右下の少し突き出た部分が「石落とし」。姫路城には81カ所あります(写真:カリーナ/PIXTA)
見どころ③ 城門
■菱の門
城内に10以上の門を持つ姫路城。その中でもっとも大きいのが「菱の門」です。安土桃山時代の様式を残しており、門を支える柱の部分に「菱」の紋があるためこの名前で呼ばれています。入城口から見える最初の門であり、来城者全員がくぐる門です。

菱の門
■るの門
もっとも大きい門は「菱の門」ですが、 もっとも小さい門は「るの門」です。敵を退けるための工夫のひとつで、人ひとりが通れるくらいのサイズです。城門の上には二階建ての櫓が載っていますが、これはほかの城郭では見られません。

大人数では通れない「るの門」(写真:たき/PIXTA)
見どころ④ 内曲輪・中曲輪
■西の丸
菱の門を抜けて左手にある庭園「西の丸」。戦国時代、戦いの前に兵士が集結する場所として使われた「武者だまり」があります。また「化粧櫓(けしょうやぐら)」にもぜひ注目を。美男で有名だった本多忠刻(ほんだ ただとき)に嫁いだ、千姫(せんひめ)のために建てられた櫓で、千姫が休息所として使っていたといわれています。

西の丸にある化粧櫓
■二の丸
菱の門のあと、正面にある「いの門」を抜けたところに広がる空間が「二の丸」です。ここには櫓や門が密集しており、敵が侵入しづらい造りになっています。また、侵入されても狭いところへ追い込みやすいよう入り組んでいます。
■備前丸
大天守の目前に広がる敷地を「備前丸」と呼びます。元々は姫路城を築城した池田輝政(いけだ てるまさ)やその家族などが住む居館が建てられていた場所でしたが、明治中期の火災で焼失してしまいました。現在は広大なスペースが残っています。
■姫路城を望む庭園として人気の「好古園」
姫路公園に行ったら訪れたいのが、園内西部にある「好古園」です。国宝・姫路城を望む庭園として人気を博しており、園内にはそれぞれ別々のテーマをもった庭園が9つ広がっています。
大きな池を錦鯉が泳ぐ「お屋敷の庭」、茶室「双樹庵」を構える「茶の庭」、紅葉を楽しめる「夏木の庭」などが人気です。「双樹庵」では実際にお菓子とお抹茶をいただくこともでき、庭園を眺めながらホッと一息つくのもおすすめです。
また、好古園内にある「レストラン 活水軒」では「姫御膳」「国産牛の陶板焼きセット」などの食事メニューがいただけるので、ランチにぴったりです。

好古園
【好古園 基本情報】
入園料:大人310円 ※姫路城とのセット券は大人1050円
公式サイト:姫路城西御屋敷跡庭園 好古園
姫路城の伝説-「お菊井戸」と「宮本武蔵の妖怪退治」
700年以上の歴史を持つ姫路城は、その歴史の長さから様々な逸話や伝説が残されています。ここでは、語り継がれる姫路城の伝説の中から有名なふたつをご紹介。
姫路城の伝説①「お菊井戸」
「お菊」という女性の亡霊が夜な夜な「お皿がいちまーい、にまーい……」と数えている、というストーリーで有名な恋愛悲劇「播州皿屋敷」。そのもの語りに深く関係している井戸が姫路城にある「お菊井戸」だといわれています。

お菊井戸
姫路城の第9代城主が小寺則職(こでら のりもと)だった時代。則職の家臣であった青山鉄山は、城の乗っ取り計画を企てます。しかしそれに気づいたのが、同じく則職の家臣だった衣笠元信(きぬがさ もとのぶ)。元信は自分の妾(めかけ)の「お菊」を青山家の女中として送り込み調べさせます。そして、お菊は青山家による則職暗殺計画を突き止め、元信らとともに未然に防ぐことに成功しました。
しかし、城に密告者がいると睨んだ青山家の家臣・町坪弾四郎(ちょうのつぼ だんしろう)は城中を調べ上げ、そしてとうとうお菊を突き止めます。そこで弾四郎はかねてより好意のあったお菊に、この事実を盾に求婚。しかしお菊はこの求婚に断固拒否。腹を建てた弾四郎は、お菊が管理していた10枚の家宝の皿を1枚だけ隠し、その罪をお菊になすりつけます。しまいには、お菊を責め殺し、井戸に投げ込んだといわれています。それからは、毎晩お菊が「お皿が1枚、2枚……」と数える声が聞こえるようになったといわれているのです(諸説あり)。
その井戸が菱の門を通って右手、備前丸の南側にあるものとされています。現在、お菊は姫路城から歩いて20分ほどの、「十二所神社」に祀られています。
姫路城の伝説②「宮本武蔵の妖怪退治」
姫路城にまつわる伝説をもうひとつご紹介しましょう。天正時代(1560年代末)から文禄年代(1580年代頃)にかけて、木下家定(きのした いえさだ)が城主をしていた頃のことです。剣豪として知られる宮本武蔵は名を隠し、姫路の地で足軽奉公(江戸時代頃の歩兵のこと)として活動していました。

剣豪・宮本武蔵と佐々木小次郎の決闘の像
当時、姫路城には妖怪が出るという噂が立ち、人々は恐れていました。しかしさすがは宮本武蔵、夜間も平気で警備にあたっていました。それが家老の耳にまで入った結果、武蔵が名高い武芸者であることが周囲に発覚してしまい、妖怪退治を命じられてしまいます。
夜になり、武蔵が城に入ると3、4階が大きな炎に囲まれ、地震のような揺れや音が起きました。武蔵が刀に手をかけると、不思議と炎と共に揺れも収まり、静けさが戻りました。その後も最上階で夜通し警備にあたっていた武蔵。あたりが明るくなってきた頃に、武蔵の前に美しい姫が現れます。彼女は自分が姫路城の守護神「刑部(おさかべ)明神」であると名乗りました。武蔵に「そなたのおかげで妖怪は去っていきました」と感謝し、郷義弘(ごう よしひろ)の名刀を授けたといいます(諸説あり)。
長い歴史を持つ姫路城だからこそ、今なお様々な逸話や伝説が語り継がれています。
姫路城の歴史 城主は誰だった?

姫路城の城主になった人物は秀吉以外にもたくさんいます
姫路城の歴史① 築城はいつ?
姫路城の歴史は1300年代にまでさかのぼります。これまでの定説では、征夷大将軍である護良親王(もりよし しんのう)の命を受けた赤松則村(あかまつ のりむら)という武将が、当時「姫山」と呼ばれていた土地に砦を構えたのが姫路城の起源とされてきました。そして、則村の次男である貞範(さだのり)が最初の城主として、砦を拡張して城を築いたと考えられていました。
しかし、最近になって発見された「正明寺文書(しょうみょうじもんじょ)」によって、永禄4年(1561年)に姫山に城もしくは屋形があったことが確認されました。
また、別の資料にも「永禄の新城」という言葉が出てくることから、天文24 年から永禄4年(1555年〜1561年)までの間に、黒田重隆(しげたか)・職隆(もとたか)父子が主君の許しを得て城を築いたのが最初ではないかと考えられています。
その後、姫路城は多くの武将によって治められてきました。1580年代には天下統一を果たした豊臣秀吉が城主を務めていたこともあり、静岡の浜松城と並んで「出世城」と呼ばれています。そして現在のような、5重7階の天守が建てられたのは、1609(慶長6)年のこと。池田輝政が城主の頃でした。
400年以上の長い歴史を誇る姫路城ですが、戦国時代、第二次世界大戦といった戦火や自然災害を逃れ、大きな被害を一度も受けたことがないのも大きな特徴です。老朽による修復や増築工事は行われましたが、美しく白い天守は、当時からずっと姫路の街を見守り続けています。

姫路城のおもな出来事年表
姫路城の歴史② 姫路城のおもな城主
初代:赤松貞範
6代:山名持豊
7代:赤松政則
10代:小寺則職
14代:黒田孝高
15代:羽柴秀吉(豊臣秀吉)
17代:木下家定
18代:池田輝政
姫路城をもっと楽しむ豆知識3選
姫路城の豆知識① 厠は使われなかった
姫路城の大天守地下階には、厠(かわや/トイレのこと)が3つあります。1階に通じる階段の下に2つ、東北側の隅に1つです。使用された痕跡はなかったそうです。
姫路城の豆知識② 台所付きの城
姫路城の地下階にはトイレだけでなく、流し台もあります。また、台所櫓へ通じる扉もあります。これらは臨戦時に備えての設備でした。現存12天守の中には井戸のある天守はありますが、台所のある天守は姫路城だけです。
姫路城の豆知識③ 改修工事と瓦
姫路城に施された様々な装飾の中でも「屋根の瓦」はちょっと特別です。兵庫県姫路市の船津町では良質な粘土が採れることから、1800年代より瓦造りが盛んに行われてきました。船津町は町になる以前、旧神崎郡の船津村という行政区分だったので、船津で作られる瓦は「神崎瓦」と呼ばれるようになります。
平成の大改修でも、船津に工場を構える光洋製瓦の瓦が使用されました。

平成の大改修中の姫路城
光洋製瓦では姫路城の瓦を瓦を作った工場の見学が可能。職人の方々から瓦についての紹介を受け、工場の中で道具を見て、触れて、瓦づくりを体感できます。また、瓦づくり体験や粘土工作体験もできます。瓦づくりでは「いぶし瓦」を、粘土工作ではしゃちほこや鬼面などを粘土でつくりあげます。
焼きあがった粘土工作の作品は後日送られるので、世界に一つの作品が作れますよ。
姫路城の観光情報-入場料・駐車場情報はこちら
姫路城 基本情報 ※2022年10月時点の情報です
住所:兵庫県姫路市本町68
時間:9:00〜17:00(16:00閉門)
休城:12月29日、30日
料金:姫路城入城 大人1000円
姫路城・好古園の入城 大人1050円
公式サイト:世界遺産 姫路城
駐車場
大手門駐車場(555台/姫路城まで徒歩10分)
大手前公園地下駐車場(323台/姫路城まで徒歩6分)ほか
公営駐車場一覧:姫路城周辺駐車場(姫路市まちづくり振興機構)
姫路城へのアクセス
①公共交通機関
JR姫新線・山陽新幹線 姫路駅から徒歩5分。または神姫バス大池台方面で5分、「姫路城大手門前」バス停で下車、徒歩7分
②車
山陽自動車道「山陽姫路東」ICから車で15分
播但道「花田」ICから車で15分
イベント情報-マラソン・ライトアップ・桜
イベント① 世界遺産姫路城マラソン
2015年からスタートしたマラソン大会です。参加できるコースは2種類あり、ひとつは大手前通りをスタートし、姫路城三の丸広場をフィニッシュとする42.195kmのマラソンコース。もうひとつは城南線(姫路護国神社付近)をスタートし、姫路城三の丸広場をフィニッシュとするファンランコースです。ファンランコースの距離は年代により1〜5kmに分かれています。
毎年夏に募集を行い、2月末に開催。参加申し込みは公式サイトからできます。
【2023年 マラソン開催情報】
日時:2023年2月26日/9:00スタート
参加期間:8月19日〜9月30日
公式サイト:世界遺産 姫路城マラソン2023
イベント② 姫路城ナイトイベント・ライトアップ
姫路城は年間を通じてライトアップを行なっていますが、毎年秋にはナイトイベントを開催。2022年は「千の願い、月への想い」というテーマで、千姫の生涯をモチーフに5ヶ所のエリアで、プロジェクションマッピングやライトアップのイベントを行います。
また2022年10月1日には乳がんの正しい知識啓発の一環で「姫路城ピンクライトアップ」を開催。ピンク色のスカイランタンもあがりました。
【2022年 ナイトイベント開催情報】
日時:2022年10月24日(月)〜11月6日(日)
時間:18:00〜21:00(20:30最終入場)
料金:大人1000円
公式サイト:姫路城ナイトイベント「シロノヒカリ」

姫路城のライトアップ
イベント③ 観桜会
姫路城は桜の名所としても知られていますが、毎年4月には観桜会を開催。琴や和太鼓の演奏が楽しめます。参加は無料です。
桜と姫路城を撮影するのにおすすめのスポットは次の通り。
■西の丸庭園「千姫の回廊」 ■三の丸回廊
■シロトピア記念公演 ■桜門橋
■東御屋敷跡公園 ほか
【2022年 観桜会開催情報】
日時:2022年4月2日/1部 10:00〜 2部 12:45〜

桜に囲まれた姫路城
姫路城をたっぷり楽しむ便利なアプリやガイド
姫路城大発見アプリ(スマートフォンアプリ)
「姫路城大発見アプリ」は、ARやCGを使った展示・解説を見ることができます。城内のアプリのマークがあるところで、スマートフォンをかざすとアニメーションが流れ出したり、豆知識を教えてくれたりします。ダウンロードは無料。
外国語ガイドも充実
姫路城では日本語および外国語のガイドの方が、城の詳しい歴史などについて教えてくれます。日本語はガイド1人につき、2,000円。外国語は地元の方のボランティアで、無料で行われています。どちらも事前予約などは不要。姫路城の受付で当日申し込みができます。
また、webサイト上での姫路城ガイドもあるので予習にもぴったり。
各種パンフレットのダウンロードはこちら
■姫路観光ナビ「ひめのみち」
■姫路市「観光パンフレットの閲覧・ダウンロード」
日本屈指の名城「白鷺城」の名を持つ姫路城
姫路城はその美しい外観を「白い鷺が羽を広げているさま」に例えられ、「白鷺(しらさぎ・はくろ)城」の愛称で親しまれてきました。改修工事が終わったこともあり、再び注目を集めている姫路城。戦国・江戸時代のお城で世界遺産に登録されているのはここ姫路城と京都の二条城だけです。また、姫路城には写真撮影スポットも多数存在します。ぜひお気に入りの撮影スポットを見つけてみてください。
大きな災害に巻き込まれず姫路の街を守ってきた歴史ある城に、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。
参考:『改訂版 姫路城のなぜ?なに?』(しろまる会)『世界遺産 国宝 姫路城』(姫路市観光企画課)ほか